

発展途上国の法制度整備を支援する人材と国際法を武器に国際社会で活躍できる人材を育成
日本法の一定の知識をベースに、発展途上国の法文化・法制史・法系や法社会・経済について多角的にとらえ、その国の課題に見合った法制度整備について考え、日本から可能な支援のありかたについて勉学します。また国際法関連科目を体系的に揃え、多国間条約交渉論や海外実習で国際法実践力を養い、国際的に通用する英語力を身につけます。卒業生は、国際機関、国際NGO、外務省、防衛省などで活躍しています。
教員からのメッセージ

教授
林美香
院生からのメッセージ

博士前期課程
中谷清続
私は国際法プログラムに所属していますが、大きな魅力が 3 点あると考えています。一つは国際法の諸分野に関するものだけでも幅広く履修できる講義です。二つめは主体的に行動する機会に富んでいることです。2016 年はイランから来日された海洋法の講師を招いて学生中心にセミナーを開催しました。三点目は国際的に学び実践できるプログラムの数々です。2016 年はアイスランドで学会発表した学生がいたほか、2017 年 1 月に私はフランスのグルノーブル大学へ交換留学しました。これらすべての特徴は私たちのグローバルなキャリアに繋がっていると感じています。
ねらい
本プログラムは、国際社会や国際協力の現場で問題となる法的課題を理論的・実践的に解明する能力をつけるための教育プログラムです。修士 (法学) または修士 (国際学) の学位を取得し、また博士後期課程に進学して、国連をはじめとする国際機関、援助機関で働くのに必要な専門的知識・能力の養成を目的とします。
国際法プログラム は、国際法専門家として国際社会で活躍できる人材を輩出できるよう、国際法基礎科目とともに人権、環境、経済などの需要の多い分野の授業科目を提供し、キャリアパス開拓を支援します。このキャリアパス開拓には、海外実習、インターンシップ等の授業科目や、国際公務員養成プログラム も利用されます。
開発法学のプログラムは、開発途上国の社会経済開発に伴う法制度の自律的形成を研究し、支援するねらいを有します。国内外の援助機関で、法と開発、ガバナンス、法の支配などをキーワードとする制度構築型の支援が急速に展開しています。このプログラムは、そうした支援の検証を行い、また地域理解に根ざした正確な比較法知識を有する人材の育成をめざします。
特色
本プログラムは、多様な授業を提供しながら、きめ細かい個別指導も行います。英語授業 や海外実習も多く、国際社会での活躍に必要な専門的語学力も身につけることができます。
国際法プログラム の第一の特色は、国際法教員が全員で連携し、集団的に教育を行っていることです。第二は体系的カリキュラムです。文献のリサーチ方法を教授する実習と教科書を英語で精読する演習で基礎力を、人権、環境、経済などの個別分野の授業により専門性を、そして多国間条約交渉論や海外実習、インターンシップなどにより実践力を養います。
開発法学プログラムは、対象諸国の法・制度形成を内側から探究する比較法的アプローチに依拠し、法社会学的現実を見つめながら、実定法の理解を深めます。実証性を重視し、日本の ODA が実施する法整備支援の事例研究やフィールドワークを行います。また、留学生と共に学ぶ機会を提供します。

カリキュラム (博士前期課程)
| 授業科目 | 単位 |
|---|---|
| 国際協力法 | 2 |
| 国際人権法 | 2 |
| 国際機構法 | 2 |
| 多国間条約交渉論 | 2 |
| 国際環境法 | 2 |
| 国際経済法 | 2 |
| 国際法外交実務論 | 2 |
| 国際協力法特論 | 2 |
| 国際協力法演習 | 4 |
| 比較法制論 | 2 |
| 国際投資法 | 2 |
| 授業科目 | 単位 |
|---|---|
| 国際協力法各論 | 2 |
| 比較法制論演習 | 4 |
| 開発人権法 | 2 |
| 法と持続的開発 | 2 |
| 開発社会法 | 2 |
| アジア環境法 | 2 |
| 法整備支援論* | 2 |
| イスラム法社会論 | 2 |
| 開発社会文化論 | 2 |
| 制度構築論特論 | 2 |
| 制度構築論演習 | 4 |
* この授業は法務省法務総合研究所国際協力部の協力で実施されます
①この表以外の研究科提供科目や認められた他研究科等の授業科目を 30 単位取得し、修士論文を提出して最終試験に合格することが、前期課程の修了要件です
②演習は 8 単位を取得することが必要です
③演習以外の授業科目は 22 単位以上取得することが必要です
④リサーチペーパーをもって修士論文に代えることができます。修士論文、リサーチペーパーともに英語による執筆も認められます


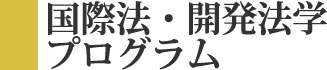


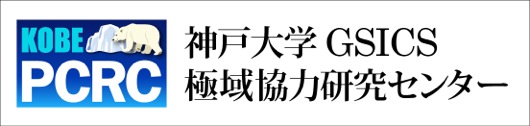


私が所属する国際法プログラムでは、合同演習で集団指導を行っているのが大きな特徴です。また GSICS では、私を含む専任教員による講義の他、外交官による「国際法外交実務論」等を毎年開講していて、国際法を幅広く体系的に学ぶことができます。指導教員と一対一で論文一筋に数年を過ごす伝統的な大学院での国際法の研究とは、まったく異なる研究スタイルを実現できる場です。